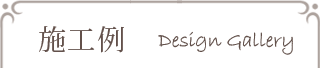HOME > スケッチブック
スケッチブック
-
***シンボルツリーを選ぶ時***風景をかえる樹 (2017/12/20)
『シンボルツリー』とはその名の通り、家のシンボルとなる木のことを言います。
お家の『シンボル』すなわち『象徴』になるのだから、家をより美しく、相互に協調しあい、美しい風景をつくり出す樹となります。
お選び頂いた木によって、家の雰囲気は大きく変わります。

だからこそ、それぞの家にとって『ベスト』な、シンボルツリーを選んでいただきたいと思うのです。
『シンボル』だからこそ、そこに暮らす人々に愛され、家族と同じように、同じ時を過ごしていく…。
弊社では、木々を選ひ頂く前に、それそれの庭の環境条件をチェックさせて頂きます。
日照はどうか・・・風通しはどうか・・・気候風土はどうか・・・。
十分な日当たりや風通しが確保できないと言う事は、植物にとって過酷な環境になってしまう事もあるのです。
1日の間に何時間ぐらい日が当たるかで、植える木の種類が変わってきます。
ただ、好きな木を植えれば良いという訳にはいきません。
人間も『適材適所』が、何より大切ですよね?

樹木も植物も同じです。それぞれの環境に応じた、樹種を選んであげる事が何より大切です。
紅葉を楽しむ木は日当たりのよい場所へ。
日陰なら耐陰性のある木々を選ばなくてはなりません。
また、寒冷地では寒さに強い木を。

逆に暖地でも、冷涼な環境を好む樹は不向きであり、諸条件に合わない樹木の植え付けは、
害虫の被害だけでなく、病気の発生が多くなる傾向がございます。
まずは、自分の庭環境の条件をよく調べておくことが大事です。
重要なことは、管理がしやすく、ある程度の大きさが維持でき、そして自然樹形を損なわない樹種の選択がベストなシンボルツリーになります♪
あなたにとっても、、樹木にとっても心地よい場所でありますように♪
Let’s enjoy the garden!
-
***シンボルツリーを選ぶ時*** (2017/12/08)
お客さまとお話しをしていて、よく話題にあがることがあります。
『シンボルツリーをどうしよう・・・』っと.

The choice of symbol tree

The choice of symbol tree
お家のイメージを左右するシンボルツリー。
庭の場合にはスペースや立地条件・環境等の関係もあり、どんな木を選んでいいのか、なかなか悩むところですが、わたくしはまず、「冬に葉っぱがある樹がお好みですか?」と伺わせて頂きます。つまりシンボルツリーは「常緑樹と落葉樹のどちらをイメージされていますか?と。

The choice of symbol tree

The choice of symbol tree
家や庭全体の印象を決めるシンボルツリーには、さまざまな役割があります。外から家を見たときの外観を引き立てる美しさだけではなく、家の中から外を眺めたときの景観も美しく演出してくれますし、庭の植物に高低差をつけることで、平坦になってしまいがちな小さな庭にも奥行きや立体感を持たせ、また広く見せる効果も期待できます。

Evergreen
ただ、どんな樹を植えるにしてもお客様のライフスタイルに合わない樹や、せっかく『シンボル』として迎えるのだから、愛されなくては樹にもお施主さまにもストレスになります。
お悩みの最大の要因は「葉っぱのお掃除!」、お掃除が楽だから「シンボルツリーは常緑樹!」とお考えの方も多いのですが…。本当に常緑樹はお掃除が楽なのでしょうか?
わたくしのアドバイスは「こまめにお掃除出来る方なら常緑樹はおすすめ」ですが、年に数回しか手を掛けたくないのなら、「落葉樹の方が断然お掃除は楽ですよ」と申しあげています。

Deciduous trees
「なんで、落葉樹が楽なの?』って不思議に思われましたか?

Evergreen
常緑樹は一年中緑が愉しめる魅力的な木ではありますが、そのかわり葉は一年中ハラリハラリと古い物から順番に葉が落ちます。
また、新芽が展開した5月~6月には、結構な量まとめて葉が脱落します。
つまり、ハラリハラリ&どっさり葉っぱが落ちます、そのため、こまめなお掃除が一年中必要になります。
落葉樹は通常11月~12月、樹種によって異なりますが、ご存じのとおり一気に「ごっそり」と落葉します。多くは約2週間の間に、脱落する樹が殆どです。つまり、この約2週間だけお掃除すればいいのですよ。私は断然!後者の「落葉樹」の方が年間のお手入れは楽だと思っています。
まあ、お掃除はともかく((笑))!冬に葉っぱがあった方がいいのか、なくても良いのかをまずイメージしてみて下さい。その上で、植栽される環境と目的、場所等を鑑みれば何がベストな『シンボルツリ-』になるのか、答えは絞れてきますよ♪
Let’s enjoy the garden!
-
植物たちの冬支度★3 (2017/12/02)
今回は『冬を知らない植物たち』の話をします♪
冬を知らない植物というのは『ラン』の一部や、ホームセンター・お花屋さんで『観葉植物』として売られていたりする植物たちのお話です。
暖かい所の生まれの植物は、年中夏!!なところで生まれ育っています。冬という季節があることを知らないのです。
日本でも、小笠原諸島や南西諸島・八重山諸島などの植物たちは『年中・夏?』 かもしれませんが~(笑)♪
「冬を知らない」ということは、冬支度のやりかたも知りません。なので、そのまま寒い戸外や冬空のもとに放っておくと、ぽけーっと夏の意識のまま、夏の姿のまま・・・。冬支度・身を守る術も知らぬまま・・・。
人でもそんな姿で冬が来たら、風邪をひいたり・病気になってしまいますよね・・・(笑)

花よりフクロウが目立ってますね~
冬を知らないために、寒さに身体がついていけないのです。
そもそ南国生まれの植物は『寒さ』を経験したことが無いのです。
そのため、【暖かくしてあげる】、という世話が特別に必要になってきます。
特別と言っても最低限以下の点を気を付けていれば多くの観葉植物は冬を越せるでしょう。
〇夜間温度が17℃を切る頃になったら室内に入れてあげる。
〇昼間は窓際のレースカーテン越しに置き、夜間の特に寒い日は室内の中心の方、暖かい所に置く
〇鉢の土が乾ききってから水を暖かい昼間のうちにあげるといった点です。人も、植物も、みんな冬支度は必要ですね!私も着々と冬を乗り切るために準備中です!
暖かくして、風邪なんて吹き飛ばしましょう!そして、冬を楽しみましょう♪
-
植物たちの冬支度★2 (2017/11/24)
今回は植物たちの冬の過ごし方についてのお話です。
春に咲く植物たちの多くは、地面近くに新芽を出してぺったりと縮こまる『ロゼッタ』状になることによって冷たい風の当たる表面積を小さくしたり、チュ-リップ等の球根類は地面の中に大半を入れることによって冬を過ごす事によって、地上よりは暖かく過ごすことができます。

冬の芝生地や草地で、地表にベッタリと張り付いて、放射状に葉を広げている小さな草を見かけたことありませんか?

植物たちの冬支度
まるで、八重咲きのバラの花びらのように見えるので、バラ(Rose)の花から由来した「ロゼット」(英:Rosette)または「ロゼット葉」と呼ばれています。越年草の場合、前年の終りに発芽し冬を越してから春に成長します。したがって、冬の間はじっと寒さに耐える必要があるので、冷たい風を避けるため地表にベッタリと張り付き、しかも太陽の光を存分に浴びるために葉を広く広げた形をしています。春になると、越年草はロゼット葉の中央から茎を伸ばして背が高くなりその頂点に花をつけます。大切な花を咲かせるために、寒い冬を越す植物たちの知恵ですね!!
しかし、寒いのがかわいそうだからといってむやみに室内で育てるのはやめましょう。

rosette
春に花を咲かせる越年草や球根類などは、
寒さを「冬が来た」という目印にしています。
冬を実感しないと、春を迎えられません。つまり、寒さに当てないと花が咲かないのです。
また、基本的に秋に肥料をやったら追加の肥料はいりません。体が小さくなった分肥料もたくさんはいらなくなっているのです。暖かくなりはじめたら肥料をあげるようにしてくださいね♪ 冬はまだまだ始まったばかり、寒い冬も植物たちは上手にのりきれる工夫をしたたかに行っています。植物たちのたくましさを見習い『たくましく』生きて行きたいと考える。今日この頃です♪
-
植物たちの冬支度★1 (2017/11/16)
だんだん寒くなってきましたね。
今回は植物たちの冬についてです。
私たち人間がコートを準備したり冬支度をするよう に植物たちも冬支度を始めます。
植物たちの冬支度?と言ってもよくわからないですよね。
でも、皆さんが秋に目にするものが実は植物たちの『冬支度』なのです。
まずは紅葉。
FBやBLOGでもきれいに色づいた葉の写真を載せていますが、
この葉の色が変わり、散る=落葉という作業が一つの冬支度です。

この落葉は、動物たちの『冬眠』に近いでしょうか。
暖かい間、葉は太陽を受けて栄養を作っています
(光合成) ←小学校で習いましたね、懐かしい!!
冬眠状態に入るということは食事をやめる、つまり光合成=食事をやめて、眠りにつきます。
なぜ光合成をやめてしまうのか、というのにはさまざまな説があり、これという説はまだないそうです。
ただ、葉は寒くなってくると、葉っぱの根元をせき止めてしまいます。
せき止められると、葉に根からの水が行かなくなり、やがて葉は枯れます。
食事をすること、食べたものをエネルギーに変える事、
これらは意外に生き物自体のエネルギーを使っています。
冬眠する動物が眠りについてエネルギーを消費しないようにしているように植物も栄養を作るエネルギーを使わないようにしているのです。

冬眠して眠っているのだからこの時期の栄養の追加や
過度な水やりは植物自体を弱めてしまうのでやめておいたほうがいいです。
-
エクステリアを考える時 (2017/11/09)
こんにちわ♪ 新建エクスプランニングの渡部です。
エクステリアを考える時、一番大きな面積を必要とするモノ・コストがかかるモノはなんでしょう?
それは、殆どのお客様のお家で「駐車場の舗装・コンクリート舗装」に掛かるコストだと思われます。新築外構工事の場合ほとんどのプランで駐車場は「コンクリート舗装」とお考えになる方が多いのは事実です。

コンクリ-ト舗装の駐車場
そこで、一つ疑問が生まれます。「なぜ駐車場の外構工事(エクステリア工事)にコンクリート舗装が選ばれるのか?」ということです。
「駐車場の外構工事」と一言にいっても、インターロッキング(色が付いたブロックを互い違いに並べたもの)や石張り(石さまざまな形に加工して貼り合わせたもの)、あるいは砂利を敷くだけのシンプルなものまであります。
その中で、駐車場の外構工事をする際にコンクリート舗装を選ばれるのは何故でしょう?

来客時の際の駐車スペース
「コンクリートは強度があり耐久性に優れている」
「ライフサイクルコストが低い」
コンクリート敷きは、安価に仕上がりますが夏場の照り返しが強く、一度温まると住居の室温が上がる、殺風景な雰囲気の床になってしまうなどのデメリットがありますが、雑草を避けることはできます。

ワンコの肉球にも優しい駐車場デザイン
上記は直ぐに思い浮かびますが、ライフサイクルコストとは、生涯費用:初期コスト+維持管理コストが低いということが、大きな理由と言えるかもしれません。

アンティークレンガを使った素敵なデザイン
でも、デメリットもあります!
温度変化による伸縮を考えて継ぎ目やスリットを必ず作らなければならないという事もございますが、スリットや伸縮目地の位置で、デザインを工夫する事も可能です。
コンクリート舗装と一言で言っても、メリット・デメリットを精査してエクステリアデザインに取り入れましょう!
-
Beautiful autumn colors (2017/11/02)
秋が深まると木々が色付き、山々が燃える様に赤や黄色に染まります。なぜ木によって色が違うのか、不思議じゃありませんか?その紅葉、なぜ起きるのかご存知ですか?「実は良く分かっていない」と言うのが本当のトコロなのだそうです。

Beautiful autumn colors
赤く「紅葉」する樹が、糖分から赤色色素のアントシアンが生成され赤くなり、黄色く「黄葉」する樹は、黄色色素のカロチノイドが目立つようになり、葉が黄色くなる事は分っているようですが、上記いずれの色にならない「褐葉」と、赤くも黄色くもならない紅葉も存在します。

Beautiful autumn colors
で、実際のところ諸説あるようですが、紅葉のメカニズムは『謎』が多いそうなのです。
まず木には一年中通して葉を付けている『常緑樹』と、一定の季節ごとに葉を落とす『落葉樹』がありますが、スギやマツ・コニファー等の『針葉樹』もございます。

Beautiful autumn color
『紅葉』と聞くと、モミジが有名ですが、モミジは赤く紅葉する代表選手と言えるでしょう。『黄葉』の代表選手は、イチョウでしょうか?両者ともに「落葉樹」ですが、狭義の意味で言うならば、落葉樹≒紅葉する、になりますが、広義の意味では『紅葉』は落葉樹だけに起こるモノではございません。

Beautiful autumn colors
植物は太陽の光を浴びて栄養を作る光合成をしていますが、光合成には太陽の光・温度・湿度が必要です。 太陽の光が少なく寒く乾燥している冬には、あまり活発に光合成することはできません。
常緑樹や針葉樹も冬なると葉の色が変化する樹木もあるのですよ!
その代表選手は常緑樹なのに真っ赤に染まる『オタフクナンテン』や『ドドナエア プルプレア』寒さが厳しくなるほど紅みが増してきます。

Beautiful autumn colors

Beautiful autumn colors
それでは、葉が一斉に落ちる落葉樹と古くなった葉が順に落ちる常緑樹の違いとは何なのでしょうか。
それは葉の寿命の違いによるものとも、言えなくはないのです。
落葉樹は冬の寒さと乾燥から身を守るために秋には葉を落とし、活動を停止します。
常緑樹は一斉に葉を落とす事はありませんが、古くなった葉が順番に落ちて行きます。
つまり、葉の命が潰える時『紅葉』するのかもしれない…と考えると、チョット切ないですね。
実りの秋…だけど、落葉した葉は新しい命を生み出す力も持っています。
自然ってすごいですね(涙)!
Let’s enjoy autumn
-
『メンテナンスフリー』ってご存知ですか? (2017/10/21)
『経年劣化』とか、『メンテナンスフリー』って言葉をって耳にしたことございますか?
言葉通り、前者は『年を経て劣化する』と言う意味と、後者は『メンテナンス要りません』と言う意味で使われています。

植栽にはレンガが似合います
写真はメンテナンスフリーと言われているレンガ、時を経て劣化(美観的に)していくと言われている化粧ブロックと普通ブロック。
この写真の化粧ブロックは、組積みされ約15~6年経過しています。

レンガ&化粧ブロック&普通ブロック
レンガと普通ブロックは約10年の時が経過していますが、」実は、、、恥ずかしながら1度も掃除はしておりません。

化粧ブロック&普通ブロック
レンガはどうでしょう、多少の汚れはありますが、美観を著しく損なっているとは言えません。
これがメンテナンスフリーと言われる所以です。

レンガ&化粧ブロック
風雪に堪えてなお、その経年事態を「味わい」へと変えていく煉瓦の魅力を感じずにはいられません。
私たちは、土から生まれた一個のレンガが無限の可能性を秘めていると考えています。

オーストラリアレンガ
そんなレンガが大好きです。
-
大人が愉しむ秋の庭 (2017/10/14)
こんにちわ!新建エクスプランニングの渡部です。『大人が愉しむ秋の庭』が相模原市緑区に完成しました!

庭を眺めて愉しむだけでなく、趣味の時間を愉しみ、時に家族や友人と語らう場として、暮らしに溶け込んだ日々を『お庭』で過ごすのを愉しむ人々が増えています。
s 様の奥様はフラワーアレンジメントを嗜んでおり、野の花の様な楚々とした草花がもともとお好きだとおっしゃっていましたので、その雰囲気を壊さぬように・・・。

アクセント・ウォール

素敵なファザードにもウリン材!
ファザードを彩るアクセントウォールも、バランスがとても大切です!異素材どうしをいかにバランス良く配置するかが、美しく仕上げる『鍵』になります。

ウリンデッキとオーニング!
もともとは『和』を感じるお庭で、樹肌の美しい株立ちの『ヒメシャラ』がシンボルツリーとなり、雑木風の野性味あふれるお庭でした。

リビングからの眺め
硬質な『ウリン』を用いて、リビング前にウッドデッキ!自然素材にしか出せない材質感でしょ!
リビングからの眺めも、明るいオーニングとシェードで一変しました。s様ご夫妻にも大変喜んで頂けました。
-
簡単!おいしい!秋植え野菜 (2017/10/05)

ベイビーリーフ Mesclun
こんにちは!新建エクスプランニングの渡部です!
夏の暑さが落ち着いてきたら、秋から冬にかけてガーデニングを始めるチャンスです♪庭を華やかにしてくれるお花もいいですが、育てるだけでなく収穫も楽しみな野菜もいいですよ!
10月は気温も下がってきて、病気や害虫の被害も減るので初心者でも野菜を育てやすい時期になります♪
自分で野菜を栽培し、収穫することは、最上級の喜びです。自分で育てた野菜は、味も格別ですよ♪
[ベイビーリーフ」としてスーパーでも見かける様になった〝リーフレタス”は、種を植えてから約30日で収穫することができる野菜です。
初心者でも簡単に育てることが可能で、お肉との相性や食感がよく、手巻きずしやサンドイッチによく利用しますが、小さなプランターでも簡単に栽培し、味わう事が出来るおすすめ野菜ですよ。

小松菜 Japanese mustard spinach
「Japanese mustard spinach」英名でも〝ジャパニーズ”の文字が入っている、『小松菜』、育て易さと、その美味しさはたまりません!
小松菜は中国原産の漬け菜の一種で、江戸時代に東京の小松川付近で栽培されていたことから、この名前になりました。関東の雑煮に欠かせない野菜で、現在も東京都を中心に、おもに関東で栽培されています。
耐寒性が強く、冬でもよく生育を続けるので、「雪菜」や「冬菜」とも呼ばれ、関西では「畑菜」とも呼ばれます。寒さには強く、冬でも生育を続け、霜にあたって一層甘みが増しておいしくなり、青菜の不足しがちな冬にとても重宝し、育てやすい野菜です。

スイスチャード Swiss char
「スイスチャード Swiss char」とは、アカザ科フダンソウ属の一年生作物で、1つの種から赤・黄・白・オレンジ色など綺麗な葉の軸が出来る珍しい葉野菜です。食べられる野菜でありながら、カラフルなのでお洒落に家庭菜園を楽しめます。
ほうれん草と同じようにおひたしなどの料理にも向いていますが、油と相性のいいので野菜炒めにもおススメです。葉は大きく、サンチェの葉にもよく似ているので、肉巻きも合います。また、ベビーリーフで収穫し、サラダに使うと食卓が多彩な色で華やかになります。
スイスチャードの種はとても固いので、ふやかすことで、芽が出やすくなります。一昼夜、水を含ませた新聞紙の中に入れておくのをおススメします。
ご紹介した秋植え野菜は、比較的に収穫までが短く、育てやすさから初心者にも安心して育てられる秋~冬に活用できる野菜です。冬の食卓を、ぜひ家庭で栽培した野菜で彩ってみてはいかがでしょうか?美味しいですよ!!!
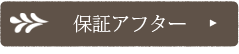
アイビーブログ
- (05.08)排除するだけの〇〇〇〇な空間も、素敵なのかもしれませんが…。
- (04.23)誕生日でしたー!
- (04.30)ピッタリで驚いた〇〇〇と、4月の夜のうれしい出来事…♡♡♡
- (04.13)イイジマムシクイの世界旅―2025
- (04.05)手が出ないと思えば思う程…(涙)